|
徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
第1号被保険者(65歳以上の人)
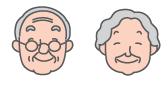 所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。 所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。
平成18年4月から、第1号被保険者の保険料の設定方法が変わりました。従来の第2段階が細分化され、負担能力の低い層に、より低い保険料率が設定されています。また、課税層についても段階設定がこれまでよりも弾力化されています。
なお、具体的な区分数や保険料率などは、市区町村の条例により設定されます。
第1号被保険者の保険料
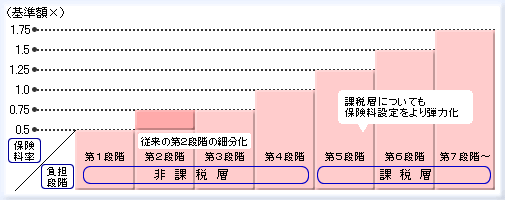
※基準額:平成21〜23年度の全国平均は4,160円(1ヵ月)
| 第1段階 |
●市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者
●生活保護受給者 |
| 第2段階 |
●市町村民税世帯非課税者で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 |
| 第3段階 |
●市町村民税世帯非課税者で、第2段階該当者以外の者 |
| 第4段階 |
●市町村民税本人非課税者 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
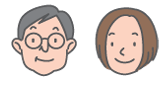 保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人(当組合では、特定被保険者本人も含む)の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は原則として折半負担です。任意継続被保険者は全額自己負担となります(賞与からの負担はありません)。 保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健康保険組合が納める介護納付金を40歳以上65歳未満の被保険者本人(当組合では、特定被保険者本人も含む)の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出されます。事業主と被保険者の負担割合は原則として折半負担です。任意継続被保険者は全額自己負担となります(賞与からの負担はありません)。
介護保険料は、健康保険組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。40歳以上65歳未満の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。
|